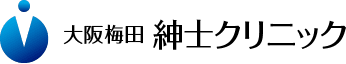- 不健康な食生活のせいでEDになるって本当?
- 食事だけで勃起不全を治す方法があれば知りたい
- バランスの良い食事をすればEDの予防ができる?
- EDにならないために避けるべき食品を教えて欲しい
そんな悩みを解決する記事を用意しました。
この記事では
- 食生活と勃起不全の関係
- 心因性EDには食事療法の効果は薄い
- EDを予防につながる栄養素6選
- EDにならないために避けるべき食品3選
といった内容について解説しています。
この記事を読むことで、食事(栄養)とEDの関係について理解し、どのようなことに気をつけて食生活を改善すればEDの改善・予防につながるかを判断できるようになります。
目次 隠す
- 偏った食事がED(勃起不全)の原因になるって本当?
- EDの予防・改善のために摂るべき栄養素6選
- EDにならないために避けるべき食事3選
- 性機能専門医が答える「EDと食事」に関するよくある質問
- Q1. 食事だけでEDは完治しますか?
- Q2. 効果が実感できるまでにどのくらいの期間がかかりますか?
- Q3. サプリメントは効果がありますか?医薬品との違いは?
- Q4. お酒は少量なら勃起機能に良いと聞きましたが本当ですか?
- Q5. 糖尿病がありますが、食事改善だけでEDは良くなりますか?
- Q6. 年齢が高くても食事改善の効果は期待できますか?
- Q7. 妻にも食事改善に協力してもらうべきでしょうか?
- Q8. 運動も同時に行った方が良いですか?
- まとめ
- ED治療薬以外にも、様々な対応が可能です。
結論からいうと、食生活の乱れが勃起不全の一因に繋がることは十分に考えられます。
正常に勃起するためには、ペニスに大量の血液が流れ込むことが必要です。
一方、EDはなんらかの原因により、血流不良が生じ、
- 性行為の際にうまく勃起しない
- 勃起が長い間持続しない
といった症状が現れる病気。
EDを起こす原因はさまざまですが、特に物理的な障害とされる「器質性ED」は背景に動脈硬化があることが多いとされています。
高血圧症、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病があると、血管の内側にコレステロールがたまりやすくなります。そして、動脈硬化が進行し、血液の流れが悪くなります。
つまり、「生活習慣病がある方は動脈硬化を起こしやすく、結果として勃起不全のリスクが高くなる」と言えます。
その生活習慣病は、不規則な生活や偏った食生活を長く続けた結果です。バランスの取れた食事をはじめとする規則的な生活が生活習慣病の予防となり、結果的にEDの予防・症状の改善につながると言えます。
また、加齢などに伴い、男性ホルモンの一種であるテストステロンが低下していきます。テストステロンは性的欲求や性的興奮、そして勃起を引き起こすために、「ドーパミン」という神経伝達物質の分泌を促す働きがあります。このテストステロンの分泌量が低下することもEDの原因の一つであると言われています。
テストステロンの分泌には食生活も深く関わっています。このホルモンは体内で合成され分泌されますが、それを担う臓器である精巣や副腎は、食生活や酒・タバコなどの生活習慣により機能が低下します。また、テストステロンの主な原料はコレステロールから作られるため、健康のためにとコレステロールを含む食べ物を避けすぎるのも、このホルモンの分泌を低下させるおそれがあります。
心因性EDは食生活と直接関係ないことが多い
一方、若い世代(10~20代)に多い「心因性ED」の症状改善には食事療法は向いていないとされています。
心因性EDは文字通り、精神的なプレッシャーにより起こるEDであり、食生活とは無関係に起きることが多いためです。
心因性EDの具体的な治療としては、
- カウンセリング
- サプリメント
- ED治療薬
- 精神安定剤
などの中から原因や症状にあったものを適切に選ぶことが必要です。心因性EDに関しても、当院で診察が可能です。
ここまでを一旦まとめると、
- 食生活が動脈硬化の原因となり、EDの症状を起こすことがある
- 食生活の改善により「器質性ED」の症状が改善されることがある
- 「心因性ED」は食生活とはあまり関係がなく、専用の治療が必要
といったことがわかります。
摂取すると勃起不全にとって良い影響がある栄養素とは、どのようなものでしょうか。
EDの予防・改善のためには…
- 亜鉛
- シトルリン
- アルギニン
- カルニチン
- DHA/EPA
- ポリフェノール
といった栄養素が手助けをしてくれる可能性が高いです。
これから、それぞれの栄養素について解説しつつ、代表的な食材の例を一緒に紹介しているので、あまり食べていない自覚があれば積極的に献立に取り入れてみてはいかがでしょうか。
亜鉛には、男性ホルモンの一種であるテストステロンの分泌を促すはたらきがあります。
体内のテストステロンには、性欲や性的興奮、そして勃起を引き起こすために、「ドーパミン」という神経伝達物質の分泌を促す働きがあります。性機能に深く関わるホルモンです。
年齢を重ねるとともにテストステロンの分泌は減少するので、加齢とともにEDになりやすいといわれています。
また、亜鉛と一緒にビタミンCを摂ることをオススメします。ビタミンCは亜鉛の吸収力を高める効果があり、一緒に食べることでより効果的に亜鉛を摂り入れることができます。
亜鉛を含む食べもの
- 牡蠣
- チーズ
- 豚肉
- 卵黄
- レバー
- 煮干し
- アーモンド
これらをレモン、ホウレンソウなどのビタミンCと一緒に摂ってみてはいかがでしょうか。
シトルリンは、遊離アミノ酸の一種で、NO(一酸化窒素)の生成を促進するはたらきがあります。
ED治療薬ほどでは無いものの、NOにも血管を拡張する(広げる)作用があり、勃起に必要な血流を促進することにも繋がります。
そのため、普段から充分にシトルリンを摂取しておくことで、ED治療薬の効果を助ける役割が期待されています。実際の研究でも「軽度のED患者がシトルリンを摂取することで半数以上に症状の改善が見られた」とするものがありました。
シトルリンを含む食べもの
- スイカ
- メロン
- きゅうり
- ゴーヤ
といった「ウリ科の植物」に多く含まれているため、意識して摂取してみましょう。
アルギニンの重要な役目は、「成長ホルモンの分泌」と「血管拡張」です。
適切に摂取することで血管拡張作用のあるNOの生成を促進することで血流が改善し「勃起力の向上」を助けると考えられていて、精力サプリなどに含まれていることが多いです。
近年では、美容分野でアンチエイジング効果が期待されていたり、疲労回復成分としてレッドブルなどのエナジードリンクに配合されています。
アルギニンを多く含む食べもの
- アーモンド
- キハダマグロ
- 鶏卵
- 高野豆腐
- 落花生
アルギニンとシトルリンはどちらも、身体の中でNOの生成を促進し、その過程で、アルギニンはシトルリンを、シトルリンはアルギニンを生成します。
つまり、これら2つを一緒に摂ることで、より効果を発揮するとされています。
カルニチンは、アミノ酸の一種で、細胞内でエネルギーを作り出すミトコンドリアへ燃料となる脂肪酸を送り込むはたらきがある栄養素です。
細胞の活性化を促すため、精子の運動率を上げるなど、男性不妊の改善のサポートとしても利用されています。
「加齢によるテストステロン欠乏に対してカルニチン(アセチル・L-カルニチンとプロピオニル・L-カルニチン)を6ヶ月間投与したところ、ホルモンの補充療法と同程度に性機能が改善した」という報告があります。
また、心機能などの循環器系の細胞障害の改善を助ける作用も報告されています。
実際の研究で、「カルニチン(プロピオニル・L-カルニチン)、L-アルギニンおよびナイアシンを3ヶ月摂取することでEDの改善が見られた」という報告があり、さらにカルニチン(アセチル・L-カルニチンおよびプロピオニル・L-カルニチン)とED治療薬シルデナフィル(バイアグラ®の成分名)を併用したED治療法の特許が取得されていて、ED治療薬の効果を助ける役割が期待されています。
L-カルニチンを含む食べもの
- 羊肉(ラム肉)
- 鶏レバー
- 牛肉
- 赤貝
肉類に多く含まれていますが、サプリメントで吸収率が高いものが開発されています。
DHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(エイコサペンタエン酸)は、青魚に多く含まれる必須脂肪酸のひとつです。
よく知られている効能として、血液をサラサラにし、中性脂肪を下げるというものがあります。これらの栄養素をバランスよく摂取できていれば、血液はサラサラになり、肥満や脂質異常症の予防になります。
血流が良くなることで、ED症状改善の助けになることが期待できます。
厚生労働省が推奨するDHA・EPAの一日当たりの目標摂取量は、2つ合わせて1000㎎以上。これらは体内でほとんど合成されない栄養素なので、食べ物やサプリメントで摂取する必要があります。
DHA・EPAを含む食べもの
- サンマ
- イワシ
- サバ
といった青魚を積極的に食べるように心がけましょう。
ポリフェノールは、強い抗酸化作用を持つ成分で、体の中の細胞を傷つける「フリーラジカル」という物質を取り除き、血管の健康を保つ働きがあります。
血管が健康で柔軟だと血流が良くなり、これがED(勃起不全)の予防や改善に役立つと考えられています。特に、赤ワインに含まれるレスベラトロールという成分は、血管を広げて血液の流れをスムーズにし、EDの改善に効果が期待されています。
また、ポリフェノールはホルモンのバランスを整える働きもあります。男性ホルモンの一つであるテストステロンの分泌を助けることで、性機能の改善にもつながる可能性があります。さらに、ポリフェノールは炎症を抑える作用も持っており、血管を傷つける慢性的な炎症を減らすことで、EDのリスクを下げる効果が期待されています。
ポリフェノールを含む食べもの
- 赤ワイン
- ダークチョコレート
- ブルーベリー
- グリーンティー
赤ワインは飲み過ぎに注意し、ダークチョコレートやブルーベリー、グリーンティーなどと組み合わせて摂りましょう。
EDの予防・改善のために摂取すべき栄養素がある一方で、避けた方が良い食事もあります。
特に器質性EDは「ペニスの血行不良」と表すこともでき、これは生活習慣病による動脈硬化が原因となっていることが多いです。
動脈硬化はEDだけでなく、最悪の場合は命にも関わるため、
- 高カロリー
- 高塩分
- 高脂肪
といった食事を避けることが大切です。
ジャンクフードをはじめとする高カロリー食品を食べ続けていると、動脈硬化を引き起こす可能性があります。
- 揚げ物
- 脂身の多い肉
- スナック菓子
- カップ麺
といった食品と摂り続けていると、血管が固くなり柔軟性が失われていきます。
正常な勃起をするには血管を拡張し、ペニスにたくさんの血液を送る必要がありますが、動脈硬化が起きているとそれができずEDの症状が出ます。
年齢や運動習慣によって摂取すべきカロリー量は異なりますが、勃起機能に不安がある方は高カロリー食品を意識して避ける方が良いでしょう。
食塩の高い食品を摂取し続けると、高血圧のリスクが高まります。
- スーパーの惣菜
- 味噌汁
- インスタント食品
といった食品は多くの塩分が含まれています。
血圧をコントロールできない状態が長く続くと、動脈硬化を引き起こします。
厚生労働省によると、高血圧の予防のために「一日の塩分摂取量を8g未満」にする必要がある、とされています。
その一方で、平成30年の国民健康・栄養調査によると、男性の一日の塩分摂取量はなんとそれより高い11.0グラム。
ほとんどの現代人は塩分を摂り過ぎているということからも、すべての男性が気をつけるべき項目と言えるでしょう。
高脂肪食、特に牛や豚などの肉類や乳製品などに含まれる飽和脂肪酸は、動脈硬化の原因になると言われています。
- ジャンクフード
- チーズ
- スイーツ
- 生クリーム
- マヨネーズ
- バター
などの食品には脂肪分がたっぷり含まれていることが多いです。
また、高脂肪食は治療薬の効果を半減させるとも言われており、脂肪の多い食事を避けることはED治療において重要です。
Q1. 食事だけでEDは完治しますか?
A. 食事改善のみでEDが完治するケースは限定的です。軽度のEDや生活習慣が主因の場合は改善が期待できますが、重度のEDや器質的要因(血管障害、神経障害など)が関与する場合は、医学的治療との併用が必要です。
症状の程度や背景を踏まえ、患者様ごとに最適な治療と食事指導を組み合わせています。食事改善は治療効果を高める重要な要素として位置づけています。
Q2. 効果が実感できるまでにどのくらいの期間がかかりますか?
A. 個人差がありますが、一般的に3ヶ月から6ヶ月程度の継続が必要です。血管機能の改善や血流改善効果が現れるまでには時間を要するためです。
ただし、以下の要因により期間は変動します:
- 年齢(若い方ほど改善が早い傾向)
- EDの重症度
- 併存疾患の有無(糖尿病、高血圧など)
- 運動習慣や禁煙などの生活習慣改善の取り組み
早期に効果を実感したい場合は、PDE5阻害薬などの治療薬との併用を検討します。
Q3. サプリメントは効果がありますか?医薬品との違いは?
A. サプリメントの効果は医薬品と比較すると限定的で、ED改善効果については十分なエビデンスがあるとは言えません。
サプリメントとして使用される成分:
- アルギニンやシトルリン:一酸化窒素経路に作用する成分ですが、ED改善効果に関しては十分なエビデンスがあるとは言えません
- 亜鉛:テストステロン産生に関与しますが、欠乏がない場合の補充効果は明確ではありません
- マカ:一部で性機能改善が報告されていますが、科学的根拠は乏しく、プラセボと同程度とする報告もあります
医薬品との主な違い:
- 効果の確実性(医薬品の方が臨床試験で証明されている)
- 安全性の保証(医薬品は厳格な試験を経ている)
- 即効性(医薬品の方が優れている)
サプリメントを検討される際は、他の薬剤との相互作用や副作用のリスクもあるため、専門医にご相談ください。
Q4. お酒は少量なら勃起機能に良いと聞きましたが本当ですか?
A. 適量のアルコールには血管拡張作用があり、一時的に勃起を促進する可能性があります。しかし、長期的な勃起機能の改善には寄与しません。
適量の目安:
- 日本酒:1合(180ml)
- ビール:中瓶1本(500ml)
- ワイン:グラス2杯程度(200ml)
過度の飲酒によるリスク:
- 神経系への悪影響
- テストステロン分泌の低下
- 血管機能の悪化
- 肝機能障害による全身への影響
EDの改善を図るには、アルコールに頼るよりも生活習慣全体の見直しが重要です。
Q5. 糖尿病がありますが、食事改善だけでEDは良くなりますか?
A. 糖尿病性EDの場合、食事改善は重要ですが、血糖コントロールと併せた総合的なアプローチが必要です。
重要なポイント:
- HbA1cの目標値維持(7.0%未満)
- 血糖値の安定化
- 糖質制限と適切な栄養バランス
- 定期的な血管機能評価
糖尿病性EDは進行性の特徴があるため、早期の専門的治療が推奨されます。糖尿病専門医と連携し、血糖管理とED治療を並行して行うことが重要です。
Q6. 年齢が高くても食事改善の効果は期待できますか?
A. 年齢に関係なく食事改善の意義はありますが、若年者と比較すると改善の程度や速度は緩やかになる傾向があります。
高齢者における食事改善のメリット:
- 血管機能の維持・改善
- 動脈硬化の進行抑制
- 全身の健康状態向上
- 他の治療法との相乗効果
年齢を問わず、生活習慣の改善によって勃起機能の改善が報告された例もありますが、個人差が大きいため専門医の評価が重要です。年齢にかかわらず改善の可能性があるため、医師と相談しながら取り組むことが重要です。
Q7. 妻にも食事改善に協力してもらうべきでしょうか?
A. パートナーの協力は治療継続の重要な要因です。食事は夫婦で共有することが多いため、家族全体での取り組みが効果的です。
パートナーとの協力があると、食生活の改善や治療継続がスムーズになる傾向があります:
- 継続しやすい食生活の実現
- 心理的サポートによるストレス軽減
- 夫婦関係の改善
パートナーとの協力は、治療の継続や心理的支えとなることが多く、食事改善の成功率も高まります。必要に応じて、パートナーの方にも生活習慣の改善点を共有することがあります。
Q8. 運動も同時に行った方が良いですか?
A. 食事改善と運動の組み合わせは相乗効果が期待できます。
推奨される運動:
- 有酸素運動:週3回、30分程度のウォーキング
- 筋力トレーニング:週2回、全身の大筋群を対象
- 骨盤底筋体操:毎日10分程度
運動による効果:
- 血流改善
- テストステロン分泌促進
- 血管内皮機能の向上
- ストレス軽減
- 体重管理
ただし、心血管疾患がある方は運動開始前に専門医への相談が必要です。
この記事では、特に動脈硬化を起こす生活習慣病がEDの主な原因であり、食生活の乱れが勃起障害を起こすきっかけになりうる、という内容を解説しました。
一方で、心因性のEDの場合は原因が別のところにあり、食生活を見直しても効果は薄いかもしれません。その場合は医師に一度相談してみることをお勧めします。
記事の後半では、摂るべき栄養素と避けるべき食事についてまとめました。
ただし、亜鉛、シトルリン、アルギニン、カルニチン、DHA・EPA、ポリフェノールといった6つの栄養素を摂るにあたり、日頃からバランスの良い食事を心がけておく必要があります。「これだけを摂っておけば大丈夫」と特定の栄養だけに偏って、他の栄養素が不足してしまっては本末転倒なので注意しておきましょう。
また、すでに動脈症状が進行してしまっている場合は、食生活の見直しのみでは改善は見込めません。その場合は医療機関で治療も受けながら、総合的に症状をコントロールしていく必要が出てきます。「食事療法のみでEDを改善したい」と考えている場合でも、まずは正確に身体の状態を把握するためにかかりつけ医にて相談してみることをお勧めします。
当院では、ED治療薬の処方も実施しておりますが、今回解説した、糖尿病や高血圧症などの生活習慣病や男性ホルモン低下の影響で、内服薬が効きづらくなってしまった患者様もいらっしゃると思います。
当院では、このような患者様のために、衝撃波で血管の新生を促しEDを根本から改善する方法や、幹細胞培養上清液治療、陰茎海綿体自己注射など様々な治療法をご用意しています。
さらに、EDの原因についての検査・治療など総合的な対応を行うことも可能です。
男性ホルモンの一種テストステロンや性機能に関わるホルモンバランスの検査をはじめとして、EDの精神的要因と関わりのある自律神経のバランスを計測する検査を実施したり、睡眠時無呼吸症候群の検査をして必要な場合は保険診療による治療を実施したりできます。検査の結果、より専門的な治療が必要な場合には提携医療機関の紹介も実施しており、様々な対応が可能です。