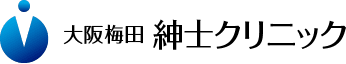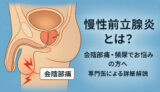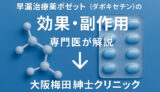「朝起きたら下着に黄色い汚れがついていた」「ペニスの先から膿のようなものが出ている」──こんな症状は、誰にも相談しにくく、大きな不安を感じてしまいますよね。でも、それは決して珍しいことではありません。
泌尿器科専門医として多くの患者さんと向き合ってきた私(平山 尚)も、「誰にも相談できず、一人で悩んでいた」「症状に気づいてから病院に行くまで時間がかかった」という声を、これまでたくさん聞いてきました。
尿道から出る分泌物は、病気、特に性感染症の重要なサインの一つです。分泌物が出たからといって必ずしも性感染症とは限りませんが、まずはその可能性をチェックすることが大切です。なぜなら、性感染症の場合、治療がご本人のみならずパートナーにも及ぶことがあり、ピンポン感染のリスクもあるため、治療経過を大きく左右することがあるからです。この記事では、泌尿器科専門医の立場から、尿道分泌物の見分け方や、その原因となる病気、そして当院での精密な診断・治療法について、医学的な根拠をもとに分かりやすくお伝えしていきます。
尿道から出る分泌物、それは正常?それとも異常?
健康な男性の尿道からも、ごく少量の分泌物が出ることがあります。これは、尿道内を清潔に保つためのもので、病気ではありません。ですが、病気が原因で出る分泌物には、明確な特徴があります。ご自身の分泌物を客観的に見てみましょう。
正常な分泌物と異常な分泌物の違い
| 特徴 | 正常な分泌物 | 異常な分泌物(病的) |
|---|---|---|
| 色 | 透明 | 透明〜乳白色、黄色、黄緑色など |
| 量 | 極少量 | 少量〜多量 |
| 粘度 | サラサラしている | サラサラ〜粘稠(ねんちゅう)な膿状 |
| におい | ほぼ無臭 | 強いにおいを伴うことがある |
| 持続性 | 継続しない | 持続的に出る、または長時間排尿しない時に目立つ |
異常な分泌物の色と性状で見分ける原因疾患
分泌物の色や粘り気は、原因となる病原体によって異なります。
- 透明〜乳白色の分泌物: サラサラして粘度が低い。量は少量〜中等量で、特に朝起きた時や、長時間排尿を我慢した後に気づきやすいのが特徴です。
→ 主な原因はクラミジア・トラコマティス。日本で最も患者数が多い性感染症の一つです。潜伏期間は1〜3週間と比較的長く、症状が軽いため、感染に気づきにくい傾向があります。 - 黄色〜黄緑色の膿性分泌物: 粘り気が強く、膿状です。量は中等量〜多量で、強いにおいを伴うことが多いです。下着に付着する汚れもはっきりわかります。
→ 主な原因は淋菌(ナイセリア・ゴノレア)。クラミジアと並ぶ代表的な性感染症です。潜伏期間は2〜7日と短く、強い排尿時の痛みや尿道の違和感を伴うことが多いため、自覚しやすいのが特徴です。 - 白色〜灰白色の分泌物: やや粘性があります。分泌量は少量〜中等量で、症状が軽微なことが多く、気づきにくいのが特徴です。
→ 主な原因はマイコプラズマ・ジェニタリウムやウレアプラズマ。これらは非クラミジア性非淋菌性尿道炎の主要な原因菌とされていますが、特にマイコプラズマ・ジェニタリウムは近年注目されており、薬剤耐性化が進んでいるため治療が難しくなることもあります。 - 血液が混入した分泌物: 見た目に明らかに血が混ざっている場合。
→ 重篤な尿道炎、外傷、稀に腫瘍性疾患の可能性があり、緊急性が高いため、すぐに医療機関を受診してください。
放置すると怖い!尿道分泌物が引き起こす合併症
「自分は性病ではないだろう」「そのうち治るだろう」と自己判断で放置してしまうと、たとえ症状が軽かったり、一度治まったように見えたりしても、病原体は身体の奥へと進んで、より深刻な合併症を引き起こすことがあります。直近で疑わしい性交渉がなかったとしても、性感染症ではないとは言い切れないこともあります。しばしば、数か月以上前の性交渉で気付かないうちに感染していた病原体が無症状のまま定着していて、時間を置いて発症するということも珍しくないからです。
ご自身が抱えるリスク
尿道炎を放置した場合の合併症について、下記にまとめました。尿道以外の部位に感染が及ぶ可能性があり、様々な症状が起こりえます。
- 精巣上体炎: 尿道炎の代表的な合併症の一つで、細菌が精巣上体にまで広がることで発症します。陰嚢の腫れや激しい痛みを伴い、高熱が出ることもあります。
- 前立腺炎: 炎症が前立腺に及ぶと、慢性化しやすく、治療が難しくなります。排尿時の痛みや頻尿、骨盤の鈍痛など、生活の質を大きく下げる原因となります。
- 尿道狭窄: 重篤な炎症によって尿道が狭くなり、排尿困難を引き起こすことがあります。
- 男性不妊症: 特にクラミジア感染症やマイコプラズマ・ジェニタリウム感染症は、精子に悪影響を及ぼし、男性不妊の原因になることが報告されています¹。
パートナーに及ぶリスク
性感染症は、無症状のままパートナーへ感染させてしまう危険性があります。特に女性では無症状感染が非常に多く、気づかないうちに病気が進行し、以下のようなリスクが高まります。
- 骨盤内炎症性疾患(PID): 子宮や卵管に炎症が広がり、下腹部の痛みや発熱を引き起こします。重症化すると、入院治療が必要になることもあります。
- 異所性妊娠: 受精卵が子宮外(主に卵管)で着床してしまう、命に関わる疾患です。
- 不妊症: 卵管の炎症によって卵子が通りにくくなり、不妊の原因となります。
早期の診断と治療は、ご自身の将来の健康だけでなく、大切なパートナーの健康を守るためにも不可欠です。
当院の診断と治療
適切な治療に繋げるためには、まず原因を正確に知ることが大切です。性感染症かどうかの見極めが、適切な治療法やパートナーへの対応を決定します。当院では、患者さんの不安を少しでも早く解消できるよう、来院当日に病原体を特定できる迅速検査システムをご用意しています。(時間帯によっては、結果が翌日になることもあります)
どのような検査をするの?
当院では、主に初尿検査で診断を行います。起床後第一尿、または4時間以上排尿を控えた後の尿を採取し、核酸増幅検査(TMA法)という高精度な検査法を用いて病原体を特定します。この方法では、4〜6時間ほどで検査結果が出ます。痛みを伴うことはなく、従来の検査方法に比べて大幅な時間短縮と、高い精度を両立しています。
当院の治療方針
診断結果に基づき、日本感染症学会や日本化学療法学会が作成したガイドライン²⁻³に準拠した治療を迅速に始めます。
- 淋菌感染症の治療: 耐性菌に対しても効果が期待できるセフトリアアキソンの点滴を1回行います。点滴後24〜48時間で症状の改善が始まり、高い治癒率が期待できます。
- クラミジア感染症の治療: 1回服用で済むアジスロマイシン、または1週間ほど服用するドキシサイクリンなど、患者さんの状況に合わせて最適な内服薬を処方します。
- マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症の治療: 近年、薬剤耐性化が問題となっているため、当院では最新の治療プロトコールに基づき、個別の薬剤感受性検査も視野に入れた治療を検討しています。安易な抗菌薬の使用は耐性菌を増やすことにも繋がるため、精密な検査に基づいた治療が重要です。
他院で治療したが改善しない難治性のケースや、複数の病原体が同時に感染しているケースにも、薬剤感受性検査に基づいた個別化治療で対応しています。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 分泌物が少量でも性感染症の可能性はありますか?
A1. はい、あります。特にクラミジア感染症やマイコプラズマ・ジェニタリウム感染症では、分泌物が非常に少量で、ご自身では気づきにくい場合があります。少しでも気になる症状があれば、検査を受けることをお勧めします。
Q2. 検査は痛いですか?
A2. 当院では主に尿検査による診断を行うため、痛みはありません。尿道スワブ(綿棒で直接拭う検査)が必要な場合も、極細の綿棒を使用し、短時間で終わるので、ごく軽い違和感程度です。
Q3. パートナーに症状がなくても検査は必要ですか?
A3. 必要です。特に女性では無症状感染が非常に多く、症状がなくても感染している可能性があります。相互の再感染を防ぐため、パートナーの検査・治療は必須です。
Q4. 治療中に性行為をしても良いですか?
A4. 治療中は、パートナーに感染させてしまう可能性があるので、性行為は控えていただくようにお願いしています。また、性行為を再開する場合でも、コンドームを正しく使用することが大切です。
Q5. 治療後に再発することはありますか?
A5. 適切な治療により完治すれば、同じ感染による再発はありません。ただし、未治療のパートナーとの性行為や、新たな性的接触により再感染する可能性はあります。
まとめ:一人で悩まず、泌尿器科専門医にご相談を
尿道分泌物は、男性にとって非常にデリケートな症状ですが、決して恥ずかしがる必要はありません。原因としては、性感染症とそうでない場合があり、まずはその鑑別のための検査が重要となってきます。
性感染症であった場合、症状を放置することの最大のリスクは、ご自身の健康を損なうだけでなく、大切なパートナーにまで感染を広げてしまうことです。特に、女性のクラミジア感染症は、不妊症の危険性を高めることが明らかになっています。
大阪梅田にお住まいの方、お勤めの方で、尿道分泌物や排尿時の違和感などにお悩みの方は、一人で悩まずに当院にご相談ください。泌尿器科専門医として、患者さん一人ひとりの症状に真摯に向き合い、最適な診療を提供します。
引用文献
¹Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021.
²日本感染症学会, 日本化学療法学会. JAID/JSC感染症治療ガイド2023.
³日本性感染症学会. 性感染症 診断・治療ガイドライン2020. 診断と治療社, 2020.
⁴厚生労働省. 感染症発生動向調査. (2025年8月14日現在)