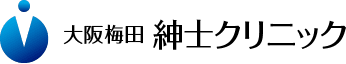- 彼女に「ブライダルチェックをして欲しい」と言われた
- 男もブライダルチェックをした方がいいの?
- 男性のブライダルチェックって何を検査をするの?
- ブライダルチェックと不妊検査の違いは?
- 男がブライダルチェックをするときの注意点を知りたい
このような疑問を解決する記事を用意しました。
記事の前半では、「男性がブライダルチェックを受ける必要性」や「特にブライダルチェックを受けるべき男性の特徴」について解説します。
また、記事の後半では、具体的に「どんな検査をどのような流れで行うのか」といった内容を紹介しています。
この記事を最後まで読むと、男性向けブライダルチェックについて理解し、実際に受けるかどうか判断しやすくなるでしょう。
ブライダルチェックとは、「これからご結婚や妊活を考えているカップル」を主な対象として、性感染症や不妊症といったリスクを事前に知っておくための健康診断のような検査です。
患者さんのご希望によって、性感染症検査・不妊検査の片方、あるいは両方を検査します。
一方、不妊検査は「妊娠を望んでいるにもかかわらず、なかなか妊娠できないカップル」が主な対象です。不妊検査が主ですが、併せて不妊を引き起こす性感染症を検査することもあります。
つまり、ブライダルチェックと不妊検査とでは、「対象となる人」が大きな違いです。不妊検査の内容に関しては医療機関によって、両者にほぼ差がない場合もあれば、ブライダルチェックよりも不妊検査でより詳細な検査をしているところもあります。
当院ではブライダルチェックと不妊検査のどちらを選んでも、同様の不妊検査を受けることができます。不妊だけではなく性感染症も心配な方は、そちらも一通りチェックできるブライダルチェックを選ばれると良いでしょう。
ブライダルチェックは結婚・妊活をきっかけに受けるもの、というイメージがあるかも知れませんが、「パートナーを性感染症から守りたい」「将来的に子供を授かりたい」と考えている方であればどなたでも、積極的にブライダルチェックを受けておくことをおすすめします。
結婚の予定やパートナーの有無などに関係なく検査を受けることが可能です。
近年では男性もブライダルチェックを受ける傾向があります。カップルで受診するケースはもちろんですが、男性専門の医療機関であれば、男性お独りでも気兼ねなく受診できます。
不妊の原因は必ずしも女性にあるわけではなく、実際には「男女それぞれに半数ずつ原因がある」と言われています。
男女別の不妊の原因について、簡単にまとめます。
- 排卵因子:卵巣から卵子が出ない
- 卵管因子:卵管が狭くなったり詰まっている
- 免疫因子:精子を無力化させてしまう
女性の不妊の原因には、上記のような要素がよく知られています。
ここで、排卵因子、卵管因子に男性因子を加えた3つが「不妊の三大原因」と言われています。(※1)
- 造精機能障害:精子の数や質に問題がある
- 性機能障害:勃起や射精に問題がある
- 精路掴障害:精子の通り道が詰まっている
男性の場合は上記の3つに分けられます。この中で、「精子(精液)」に関する原因により男性不妊となっていたものが全体の80%以上(※2)を占めていました。
不妊は男性側にも原因があることを理解し、「主に女性側の問題だ」と考えることなく、積極的にブライダルチェックや不妊検査を受けることで、ご自身の抱えるリスクを早期に発見することが出来ます。
詳しくは、下記の記事もご覧ください。
 妊活のためにすべきこと!不妊の原因の半分は男性?
妊活のためにすべきこと!不妊の原因の半分は男性?
(1) 日本生殖医学会. http://www.jsrm.or.jp/public/funinsho_qa04.html, (2023-04-22閲覧)
(2) 湯村 寧: 平成27年度厚生労働省子ども・子育て支援推進調査 我が国における男性不妊に対する検査・治療に関する調査研究. 2016
以下のような特徴を持つ男性は、積極的にブライダルチェックを受けた方がいいかも知れません。
- 年齢が高め
- 性感染症にかかったことがある
- タバコを吸っている
それぞれについて、詳しく解説します。
男性の年齢は「精子の質」に影響します。
具体的に言うと、加齢により、以下のようなリスクが高まります。
- DNAが破損した精子が増える
- 精子の数(精子濃度)が減る
- 精子の動きが悪くなる
年を取ると精子の質が低下し、正常に受精ができず流産を起こしたり赤ちゃんが先天異常を持つ可能性が高くなる、とされています。
そのため、年齢が高めの男性は、早めに精子の状態を把握するのが理想的です。
「30代後半になると、男性不妊のリスクが高まる」という研究結果(※3)もあるため、35歳以上の男性はブライダルチェックを受けておくのがよいでしょう。
(3) D. Dunson. Increased Infertility With Age in Men and Women. Obstetrics and Gynecology. 2004 Jan;103(1):51-6.
クラミジアや淋病などの性感染症は、男性の生殖器に炎症を起こし、精子の質に影響を与える可能性があります。
特に「感染が長期間にわたって続く」「感染が何度も再発する」というケースでは、精子の質が損なわれるリスクが高くなっています。
また、性感染症は性行為を通して女性にも感染し、卵管や子宮にも炎症を引き起こすことがあります。
つまり、性感染症の既往歴のある男性は、自分だけでなくパートナーの健康のためにも、ブライダルチェックを受けるべき、と言えるでしょう。
「タバコが男性の生殖機能に影響を及ぼす」ということが多くの研究で示されています。
例えば、962人の男性への研究(※4)で「タバコを吸う男性は、タバコを吸わない男性に比べて、精子の運動能力が低く、精子が変形する確率は高く、また精子の数が減少しやすい」ことを示しました。
この理由として、タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素の作用が考えられます。
それらの物質が血管を収縮させて血液の流れを悪くし、精巣へ酸素や栄養が届きにくくなった結果、精子の量や質が低下してしまいます。
(4) J. Dai. The hazardous effects of tobacco smoking on male fertility. Asian Journal of Andrology. 2015, 17, 954–960
男性向けブライダルチェックで行う検査項目は、大きく分けると以下の2種類があります。これらの検査は子作りを考えるカップルにとって重要であり、男性もブライダルチェックを受けておくのがよい、といえるでしょう。
男性不妊のチェック
現代人は精子数が減少しているという報告(※5,6)があり、精子の状態を把握しておくことが大切です。また、精子の状態に影響を与えるホルモンバランスや栄養状態の検査を行うこともあります。
性感染症
「性感染症」は、一般的に排尿痛や発疹など伴うものの、無症状で感染に気づかないこともあります。万が一、女性に感染させてしまうと、妊娠したときに胎児にも影響を与える可能性があり、注意が必要です。
(5) H. Levine. Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-regression analysis. Human Reproduction Update. Volume 23, Issue 6, November-December 2017, Pages 646–659
(6) H. Levine.Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-regression analysis of samples collected globally in the 20th and 21st centuries. Human Reproduction Update. 2023, Vol.29, No.2, pp. 157–176.
ブライダルチェックにおいて男性不妊かどうかを調べるため、初期段階では以下のような検査があります。
- 一般精液検査
- 精子DFI(DNA断片化指数)・ORP(酸化還元電位)検査
- 血液検査(ホルモン検査)
当院、大阪梅田紳士クリニックの検査項目を例に取り、詳しく見て行きましょう。
一般精液検査・精子DFI・ORP検査
一般精液検査は、ほとんどのブライダルチェックで行われている検査です。受診時に手渡される専用の容器に患者様ご自身で精液を採取して、医療機関へ提出します。
検査では顕微鏡や検査機器により、精子の数や動きなどをチェックし、以下のような情報が明らかになります。
- 精液量 :1回の射精における精液の量。非常に少ない場合は射精機能の以上が疑われます。
- 精子濃度 :精液1mlに精子が何個含まれるか。精子が少なければ卵子へ到達できる精子の数も少なくなります。
- 総精子数 :精子濃度が高くなくとも精液量が多ければ精子数は多くなります。
- 精子運動率 :運動している精子の割合。運動していない精子は卵子まで到達できません。
- 前進運動率 :上記のうち高速で直進している精子の割合。卵子までの到達・受精に関わります。
- 正常形態率・生存率 :顕微鏡では人間の主観での評価になってしまうため、運動率などから装置が推測した数値を記載する検査方式が多いです。
この検査により、精子が正常に生成されているか、卵子と受精する能力があるか、などがわかります。
また、上記に加えて、昨今の晩婚化や精子の質の低下に伴い、下記のような検査も重要になってきています。
- 精子DFI(DNA断片化指数)検査 :精子内のDNAの損傷度合いの検査。生活習慣や環境により体内で発生する酸化ストレスなどで精子のDNAが損傷を受けると受精率や着床率が低下するおそれがあります。
- 精液ORP(酸化還元電位)測定 :精液内の酸化ストレスの度合いを測定する検査。酸化ストレス度が高いほど、精子のDNAや細胞膜が損傷を受けやすくなり、状態が悪化します。
各検査項目にはWHOが定める基準値や、各検査方式独自の基準値なども設定されていますが、基準をクリアしているからと言って必ず妊娠できるということではなく、逆にクリアできていないから即自然妊娠は不可能ということでもありません。
血液検査(ホルモン検査)
血液検査により精子を造り出す能力に関係するホルモンのバランスや、精子の質に関わる栄養素が不足していないかを調べる検査です。検査項目には、以下のようなものがあります。
- プロラクチン:脳の下垂体から分泌される、乳汁を分泌するためのホルモンです。女性の授乳時期に多く分泌されますが、男性でも分泌されます。ストレス・薬剤・下垂体腫瘍などで高値になり、男女とも不妊の原因になることがあります。
- LH(黄体形成ホルモン):下垂体から分泌され、精巣のライディッヒ細胞に「男性ホルモンを作りなさい」と命令を出すホルモンです。精液検査と併せて判断することになりますが、低値では下垂体の異常、高値では精巣機能の異常が疑われることがあります。
- FSH(卵胞刺激ホルモン):脳の下垂体から分泌され、精巣のセルトリ細胞に「精子を作りなさい」と命令を出すホルモンです。精液検査と併せて判断することになりますが、低値では下垂体の異常、高値では精巣機能の異常が疑われることがあります。
- テストステロン:テストステロンは精巣のライディッヒ細胞で作られ、男性ホルモンの代表とされています。精力や精巣機能、すなわち精子を作り出す力を高めるために必要なホルモンです。
- ビタミンD:ビタミンDは、精子内細胞へのカルシウム吸収を促進することで、精子運動率を高め、静止が卵子の中に進入するための先体反応を引き起こすことが確認されたという研究報告があります。ビタミンDの摂取によって、精子の前進運動能力を改善が期待できます。
- 銅・亜鉛・セレン:亜鉛・銅・セレンは、男性の精巣発達を促し、男性ホルモンの分泌レベルを増大させます。また、セレンは精子の形成、運動性などに関与します。セレン不足は同じ必須微量元素である銅・カドミウム・鉛の不足と同様男性不妊症の原因となり得ます。特に現代人は、亜鉛不足傾向にあると言われています。
- カルニチン:脂質からエネルギーに変換する際に必要な栄養素ですが、積極的に摂取することで精子の運動率の向上が期待されます。年齢とともに減少傾向となります。
- 中性脂肪・コレステロール:基準値から高いほど、酸化ストレスの影響が増大し、善玉コレステロール(HDL)が低すぎるとコレステロールを原料とするテストステロンが低下します。精子の質、特に精子の形成に悪影響となります。
- その他:その後の治療を考慮し、肝機能や腎機能の数値の一部や、テストステロンとは異なる男性ホルモンの一種などを検査します。
例えば、テストステロンや性腺刺激ホルモン(LH、FSH)は、精子の生成を促したり、精子の成熟度を高める作用があります。
しかし、ストレスや加齢、病気などでホルモンバランスが乱れると、精子の量が減ったり、質が落ちることがあります。
超音波検査(エコー検査)について
精液検査結果に問題が無ければ必要ありませんが、精子をつくる造精機能の異常や精索静脈瘤(※)の疑いがある場合には、保険適用で超音波検査を実施する場合があります。
超音波検査により、主に「精巣」に問題がないかをチェックします。超音波検査は痛みを伴わず、リアルタイムに臓器や血流を観察できるのが特徴です。
精巣の大きさや状態を観察したり、精索静脈瘤により精巣上部の静脈の流れに異常がないかを診断することが可能です。
- 精巣の大きさ(上下・前後)は正常か
- 精巣内に腫瘍や結石はないか
- 精子の通り道に問題はないか
※精索静脈瘤とは、精巣から血液を送り出す静脈がこぶのようなもので塞がっている状態を言います。精巣内をうまく冷やすことができず精子を作る働きが弱まります。
性感染症のチェックでは「性行為により感染する可能性のある病気がないか」チェックします。当院では以下のような検査を実施しています。
- 淋菌・クラミジア(咽頭)
- 淋菌・クラミジア(尿)
- トリコモナス
- ウレアプラズマ・マイコプラズマ
- 梅毒
- B型・C型肝炎
- HIV
- HTLV-1
- 性器カンジダ症
- HPV(ヒトパピローマウイルス)ローリスク・ハイリスク
男性側に上記の感染症があると、性行為を通じてパートナーにも感染するおそれがあります。
淋病やクラミジアのように女性が感染しても自覚症状が少ない感染症もあり、気付かないうちに症状が悪化して不妊の原因ととなることも。さらに、母体を通じて赤ちゃんに悪影響を及ぼすものもあり、生まれてくるお子様に深刻な障害を引き起こす危険性があります。
通常の性感染症検査ではあまり知られていませんが、ウレアプラズマ感染症とヒトパピローマウイルス(HPV)も、男性不妊症との関連性を示唆する文献もいくつかあるため、ブライダルチェックをする上では、注意しておくべき項目となります。
大切なパートナーとお子様を性感染症から守りたいと考えている男性は、検査を受けることを検討した方が良いかも知れません。
男性不妊とウレアプラズマ感染症とヒトパピローマウイルス(HPV)の関係
ウレアプラズマは尿道炎の原因菌として知られていますが、近年、男性不妊症患者の精液から高頻度に検出され、感染していると精子の運動率の低下や形態異常、DNA損傷の増加が報告されています1,2。これは、感染による炎症で活性酸素が増えることで、精子にダメージが及ぶためと考えられています。
一方、HPVは子宮頸がんの原因ウイルスとして広く知られていますが、男性の精液からも検出されることがあり、精子のDNA断片化や受精率の低下、さらには流産リスクとの関連も指摘されています3,4。
参考文献
- Liu J, Wang Q, Ji X, Guo S, Dai Y, Zhang Z. The correlation between Ureaplasma urealyticum infection and sperm quality in infertile men. Fertil Steril. 2014;102(4):1153-1157.
- Potts JM, Sharma R, Pasqualotto F, Nelson D, Hall G, Agarwal A. Association of Ureaplasma urealyticum infection with altered semen quality in infertile men. Urology. 2000;55(4):486-491.
- Foresta C, Garolla A, Zuccarello D, Pizzol D, Moretti A, Barzon L, Palù G. Human papillomavirus found in sperm head of young adult males affects the progressive motility. Fertil Steril. 2010;93(3):802-806.
- Garolla A, Pizzol D, Bertoldo A, De Toni L, Barzon L, Foresta C. Sperm viral infection and male infertility: focus on human papillomavirus (HPV). Int J Mol Sci. 2013;14(7):15085-15092.
ブライダルチェックの検査を受ける時はどのような流れになるのか、気になる方もいらっしゃると思います。当院における検査の流れを例に、その概要を見てみましょう。
① 受付・問診
当院ではブライダルチェックの検査実施は、不妊検査・性感染症検査ともに予約不要です。医療機関によっては予約が必要な場合もあります。
精液検査については、2~3日の射精をしない「禁欲期間」が必要です。禁欲期間が長すぎると精子が劣化するという報告もありますので、当院では3日以内に留めていただくようお願いしています。
感染症検査は、尿の採取が必要な検査が含まれる場合がほとんどです。排尿が可能な状態で受診するようにしましょう。
問診票には過去にかかった病気、現在治療中の病気、服用しているお薬などの一般的な内容をご記入いただきます。精液検査を希望される場合は、妊活状況や風疹(おたふくかぜ)の既往歴などを質問する専用の問診表もあります。
また、医師や看護師から検査内容や注意点などの説明を受けます。わからないことや不安なことがあれば、ここで質問しておきましょう。
② 検査
各検査項目については本記事でご紹介しています。検査の詳細をもう一度ご覧になるにはこちら。
精液検査の実施について
当院にてお渡しする採取容器に精液を採取してください。ご自宅の落ち着いた環境での採取が望ましいですが、射精後の精子は急速に劣化するため、採取後2時間以内にご提出が難しい場合は近隣での採取が必要となります。精液の採取・提出は後日でも構いません。
ご自身で用意された容器やコンドームなどにより採取した検体は、不純物・雑菌の混入や、精液量が正しく測れないことがありますので、当院では検査をお受けできません。
ホルモン等血液検査:ご来院当日に血液の採取を実施します。
性感染症検査:ご来院当日に尿・血液・皮膚擦過の検体を採取します。排尿が可能な状態でご来院ください。
③ 結果
当院では、検査結果はおおよそ以下の日数で出揃います。
| 一般精液検査 | 採取当日 |
| 精子DFI・ORP検査 | 14~21日 |
| ホルモン等血液検査 | 約14日 |
| 性感染症検査 | 10~14日 |
検査結果は直接の手渡しのほかEメールで送信することが可能です。
検査結果によっては、不妊のリスクや性感染症への感染が明らかになることもあります。
その場合は、再度クリニックを受診し、今後の治療・対策について専門医と相談しながら選んで行くことになります。
ブライダルチェックでは、症状の有無に関わらず検査を行います。そのため、健康診断と同様に検査費用は保険適用外であり、全額自己負担となります。
ただし、不妊検査については何度かの検査で不妊症の診断が確定すれば、それ以降の検査や治療の費用のほとんどは保険適用となることが多いです。自費で実施した検査についても、自治体によっては助成金の申請が可能な場合があります。
保険適用外の自費診療は自由診療とも呼ばれる通り、同じ検査でも医療機関によって設定している費用が違います。それに加えて同じ不妊検査や性感染症検査でも検査項目は医療機関により異なる場合があります。
また、一見すると精液検査の費用が安いように見えても、不妊治療に対応していない医療機関だったり、他の高額な検査や治療との組み合わせが前提の料金だったりすることもあります。
クリニックの規模や設備、検査結果に応じて診療にあたる医師の専門性、立地によって費用には差があるため、事前に調べておくようにしましょう。
当院のブライダルチェックの料金は以下の通りです。セット価格では5000~8000円程度、通常よりも値引きがあります。
| 一般精液検査 | 10,000円(2回目から6800円) |
| 精子DFI・ORP検査(一般精液検査が無料で付属) | 25,000円 |
| ホルモン等血液検査 | 18,000円 |
| 性感染症検査 | 50,000円 |
| 男性不妊セット(精子DFI・ORP+ホルモン検査) | 38,000円(5000円引) |
| ブライダルチェック(一般精液+感染症検査セット) | 55,000円(5000円引) |
| プレミアムブライダルチェック(上記すべてを含むセット) | 80,000円(8000円引) |
この記事では以下の内容について解説しました。
- ブライダルチェックとは
- 不妊は男性にも原因があること
- ブライダルチェックを受けるべき男性の特徴
- 男性向けブライダルチェックの検査項目
- 男性向けブライダルチェックの検査の流れ
- ブライダルチェックの費用
不妊の原因の半数は男性にあり、男性側の原因の80%以上が精子または精液の異常によるものとされています。「将来子どもを作りたい」と考えている方は、一度「一般精液検査」だけでも受けてみてはいかがでしょうか。
さらに、以下の条件にあてはまる方は特に積極的に不妊検査やブライダルチェックを受けておくことをおすすめします。
- 年齢が35歳以上
- 性感染症にかかったことがある
- タバコを吸っている
ブライダルチェックには、男性不妊の検査だけではなく、性感染症の検査もあります。
女性に感染させてしまうと生殖機能に悪影響を与えるものもあり、妊娠・出産となった場合、お母さんの健康に影響するのはもちろん、赤ちゃんの先天異常や流産のリスクが高くなってしまいます。「性感染症からパートナーを守りたい」と言う方は、積極的に検査を受けておきましょう。